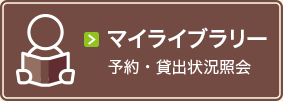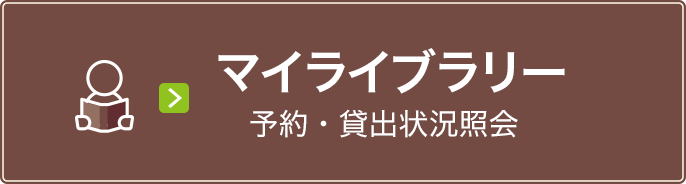令和7年度 中国・四国地区 図書館地区別研修
趣旨
情報化の進展など図書館に関する最新のテーマや地域における課題等について研修を行い、図書館における中堅の司書としての力量を高めることを目的とします。 → 開催要項(PDF)
主催等
主催:文部科学省、岡山県教育委員会
協力:公益財団法人日本図書館協会、全国公共図書館協議会
主管:岡山県立図書館
日時
令和7年12月9日(火)
~12日(金)
会場
岡山県立図書館 2階 多目的ホール
〒700-0823 岡山市北区丸の内2丁目6-30
※オンライン(「Zoom」によるライブ配信)での受講も可能です。(一部を除く)
受講対象
-
図書館法第2条に規定する図書館に勤務する司書で、勤務経験が概ね3年以上の者
若しくは研修テーマに関連する業務に従事している者 - 上記 1 と同等の職務を行っていると岡山県教育委員会が認めた者
定員
280名(会場での受講80名、オンラインによる受講200名)
受講者の決定については、修了証書の取得(「修了証書」の項参照)を目的とする方を優先させていただきます。
参加費
無料
修了証書
研修日程の概ね4/5以上を受講し、業務の改善提案・活用方法(研修内容、研修成果を踏まえた提案等)について、研修終了後2週間以内にレポート(1,200字程度)を提出した方に修了証書を授与します。
なお、オンライン受講についても同様の取り扱いとしますが、受講者の視聴環境により受講できなかった場合は、修了証書を授与できない場合があります。
研修日程
| 12/9(火) | 研修内容 |
|---|---|
| 13:00~ | 受付 |
| 13:30~13:40 | 開講式 |
| 13:40~14:45 |
文部科学省行政説明(60分) 図書館行政の動向 |
| 14:45~16:45 |
【基調講演】(120分) つなげる図書館づくり -アメリカの事例に学ぶ |
| 12/10(水) | 研修内容 |
|---|---|
| 9:30~ | 受付 |
| 10:00~ |
【①講義】(120分) 災害と図書館 |
| 12:00~ | 休憩 |
| 13:00~ |
【②講義】(120分) ICTを活用した読書支援-バリアフリーの多様な世界- |
| 15:00~ | 休憩 |
| 15:15~ |
【事例発表➀】※(45分) あそびの生まれる図書館~みんなが当事者になる場へ~ |
| 16:00~16:45 |
【事例発表②】(45分) 文学による心豊かなまちづくり ~ユネスコ創造都市ネットワーク・文学分野加盟を経て~ |
| 12/11(木) | 研修内容 |
|---|---|
| 9:30~ | 受付 |
| 10:00~ |
【③講義・演習】(120分) 必要な人へ図書館サービスを届けるには |
| 12:00~ | 休憩 |
| 13:00~ |
【④講義】(120分) 公立図書館の所蔵傾向、および新刊書籍市場の関係と書店支援 |
| 15:00~ | 休憩 |
| 15:15~ | 【施設見学】※(45分) |
| 12/12(金) | 研修内容 |
|---|---|
| 9:30~ | 受付 |
| 10:00~ |
【⑤講義】(120分) 図書館におけるAI活用の可能性:歴史的経緯等を踏まえて |
| 12:00~ | 閉講式 |
※は、オンライン受講がありません。現地のみとなります。
研修内容
| 【基調講演】 つなげる図書館づくり―アメリカの事例に学ぶ | |
|---|---|
| 講師 | 豊田 恭子(東京農業大学 教授) |
| 内容 | 分断の進むアメリカでは、図書館員が地域に出ていき、人々と文化や歴史、組織をつなぎ、何とか町を再建しようと奮闘しています。そうした事例を学びながら、これからの日本の公共図書館サービスについて考えます。 |
| 【講義➀】 災害と図書館 | |
|---|---|
| 講師 | 加藤 孔敬(名取市図書館 館長) |
| 内容 | 図書館における災害への認識として、近年の図書館の被害状況について報告します。そこから、防災・減災について考えます。 |
| 【講義②】 ICTを活用した読書支援-読書バリアフリーの多様な世界- | |
|---|---|
| 講師 | 平林 ルミ(学びプラネット合同会社 代表社員 ※オンラインでの講義) |
| 内容 | 学校の図書の時間がつらい、本を読むのが楽しくないという子どもがいます。本講座では、ディスレクシア(読み障害)の子どもたちと読書を取り上げ、読むことが苦手でも楽しく読書をするための具体的なステップを紹介します。スマホ・タブレットといったICT機器の登場で、身近にある道具を使って耳から聞く読書ができる時代になりました。これまで読書バリアフリーに関わって来られた方も、そうでない方も、読書バリアフリーの多様な世界をのぞきにいらしてください。 |
| 【事例発表➀】 あそびの生まれる図書館~みんなが当事者になる場へ~ | |
|---|---|
| 講師 | 西川 正(真庭市立中央図書館 館長) |
| 内容 | 図書館が、市民が気軽に集い学べる「居場所」として、また、地域課題について考え、行動する「出番づくりの場」としてどう応えてきたか、市民や地域の団体と協働で取り組んだ事例を紹介します。 |
| 【事例発表②】 文学による心豊かなまちづくり ~ユネスコ創造都市ネットワーク・文学分野加盟を経て~ |
|
|---|---|
| 講師 | 流尾 正亮(岡山市役所 スポーツ文化局 文化振興課 主査) |
| 内容 | 岡山市は2023年10月に「ユネスコ創造都市ネットワーク・文学分野」に加盟しました。加盟に向けて取り組んだことや加盟後に様々な方と協働で力を入れている事業等についてご紹介します。 |
| 【講義・演習③】 必要な人へ図書館サービスを届けるには ※事前課題あり | |
|---|---|
| 講師 | 赤山 みほ(近畿大学通信教育部 非常勤講師) |
| 内容 | 図書館は、誰もが毎日利用できる公共サービスである。充実した図書館サービスがあったとしても、必要な人へ届いていないあるいは利用してもらえないのでは意味がない。必要な人へ届いていないのは、図書館の広報不足や情報ニーズに合っていない等といった理由が挙げられる。そこで、本講義では、地域の事情に沿い情報ニーズに合った図書館サービスについて検討し、必要な人へ届ける広報について話し合う。 |
| 【講義④】 公立図書館の所蔵傾向、および新刊書籍市場の関係と書店支援 | |
|---|---|
| 講師 | 大場 博幸(日本大学文理学部 教授) |
| 内容 | 過去四半世紀にわたり図書館によるベストセラーの複本所蔵は批判を招いてきた。また蔵書に政治的な偏向があるとも疑われてきた。この研修では、実証データに基づいた平均的な蔵書傾向を示し、偏りや書籍市場への影響の実態について明らかにする。あわせて、近年政府が主導する書店支援の動向についても報告する。 |
| 【講義⑤】 図書館におけるAI活用の可能性:歴史的経緯等を踏まえて | |
|---|---|
| 講師 | 岡部 晋典(図書館総合研究所 主任研究員) |
| 内容 | 現在、生成AIの図書館における活用の可能性が探られている。本講義では生成AIの基本的な仕組みや特性、これまでのAIとの違いを概観し、図書館での活用可能性と適用してはならない領域等について探る。 |
参加申込
- 申込方法
インターネット(参加申込フォーム)でお申し込みください。
※申込時にご記入いただいた氏名等は、講師及び参加者に配付します。 - 申込期限
令和7年10月31日(金) - 申込・問合せ先
岡山県立図書館 図書館振興課 図書館支援班(担当:久安、島津屋)
住所 〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内二丁目6-30
電話 086-224-1269
電子メール kento01◇pref.okayama.lg.jp(◇を@に変更して送信してください)
宿泊等
宿泊は、各自で手配をお願いします。
研修の中止等について
自然災害等の諸事情により開催が困難と認められる場合は、研修を中止します。その際はメールでお知らせします。
オンライン受講について
Zoom入室に必要な情報(URL、ミーティングID、パスコード等)は、受講決定後にお知らせします。
事前の接続テストが必要な方は、各自テストサイトにて実施してください。
なお、電波やネットワークの不具合等によって発生した研修機会の逸失に対する補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
会場へのアクセス

[岡山駅から公共交通機関をご利用の場合]
●路面電車 東山行き「県庁通り」下車 徒歩5分
●バス
岡山県庁経由のバスに乗車、「県庁前」下車すぐ
・岡電バス ・宇野バス ・両備バス
[自家用車をご利用の場合]
●山陽自動車道岡山インターチェンジから約20分。
●図書館駐車場(建物の北側と西側から入れます。)は、地上81台、地下91台、合計172台ありますが、可能な限り公共交通機関でのご来館をお願いします。
その他・留意事項
- 所属で使用の名札をご持参ください。
- 事前課題は、申込終了後に受講者へ配付します。
開館カレンダー
- 土曜日・日曜日・祝日
- 休館日
<閲覧室の開館時間>
| 火曜日から金曜日 | 9:00-19:00 |
|---|---|
| 土曜日・日曜日 ・祝日 |
10:00-18:00 |
| 【お問い合わせ先】 |
|---|
| 086-224-1286(代表) |
| 直通電話番号一覧 |
| 問い合わせ内容 |
|---|
| ○調べもの相談(レファレンス) ○資料の予約・リクエスト ○貸出期間の延長 ○利用者カードの登録・更新・紛失 ○デイジー図書、対面朗読サービス カウンター:086-224-1288 |
| ○有料貸出施設の利用 (多目的ホール・情報シアター・ サークル活動室・メディア工房) ○施設見学 086-224-1286 |
| ○図書の寄贈 086-224-1324 |
| ○県立図書館以外でのお受け取り 資料 086-224-1287 |